そして偶然にも演技レッスンで扱っていた台本も、二人の朗読劇用のもの。
ナレーションのレッスンでも物語の朗読を扱った時間がありました。
これまで舞台のジャンルとしての『朗読劇』をよく知らなかったのですが、
去年1年間でいろいろ観て、すごく興味がわきました。
いつかやってみたいな、朗読劇。
今日読んでいた本も朗読関連のものです。
『ディケンズ公開朗読台本』(英光社)
チャールズ・ディケンズ本人が朗読用に仕上げた台本を日本語にし、
それぞれの解説がつけられて本にまとめられています。
日本語訳は梅宮創造さんです。
ディケンズは、『クリスマス・キャロル』の作者として有名ですね。
作家であったディケンズですが、
自作の小説を朗読用の台本に自分で書きなおし、
そして自分自身で朗読をするという活動も行っていたのだそうです。
「19世紀の英国の識字率は1840年の時点で男性が67%、女性が51%。」
この数字だけを見ても、朗読が人々に求められていたことに納得です。
さらに、本を「個人で黙読するよりも、他人と一緒に楽しむという様式が浸透していた。」というのですから、今とはちょっと違う雰囲気ですね。
「家族の団欒として朗読が行われていたり、親が子に本を読んでやったり、酒場では新聞を朗読する雇いの読み手などもあったり」と、いろいろな場面で朗読が行われていたようです。今のテレビのような役割も担っていたということになるでしょうか。
ディケンズが自作の台本を自分で朗読するというところにも大きな意味があって、
叶わぬ願いですが、ディケンズの声での朗読をぜひ聴いてみたかったなと思いました。
ピアノの演奏で、私が大好きな作曲家でありピアニストだったセルゲイ・ラフマニノフという人がいるのですが、彼が自作の曲を演奏した録音が残っています。
CDになっていて我が家にもあるのですが、作曲者本人がこう演奏しているということがわかれば、解釈の答えを明示してもらったようなものでしょう。
それでも同じラフマニノフの曲を演奏した多数のピアニストが提示してきた音楽は多種多様に聴こえるのです。
同じ文字でも読み方1つで随分雰囲気が異なります。
解釈と表現の楽しみは、表現者の力量に委ねられるわけですが、
ある範囲の中で最大限に表現していくのが、
台本ありき楽譜ありきの時の、表現者としての楽しさの1つかなと思います。
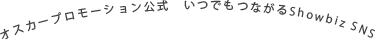

 Login
Login
 0 いいね
0 いいね クリップする
クリップする マイアミ―になる
マイアミ―になる











僕も実は年末仕事納めの日に火鍋行きました。辛いけど美味しいですよね。ビールが進みます。
ところでディケンズの朗読聞いてみたいですね。ディケンズというとイギリスの名優アレックギネスが浮かびます。彼の朗読とか残っていそうです。
ラフマニノフは僕も好きですよ。エリックカルメンという人が彼のメロディを拝借してヒット曲を書いています。
僕は今あらためてグレングールドのバッハを聴いています。もっとも作曲者に忠実な解釈ともいわれていますが個性あふれる演奏ですね。
鈴木さんは理論的に突き詰めて解釈して表現するタイプですか?
直感で表現するタイプですか?どちらにも興味がありますね。