彼女はフラフラとバスに乗り込むと、車内に客は居らず、貸しきり状態だった。
彼女は最後尾の端に腰を下ろすと、冷たく固まっていた指先に息を吹きかけ、窓の外に目をやった。
辺りはとっくに暮れていて、寒空の下、道行く人は美しく彩られた街路樹のイルミネーションに足を止めている。
二人で肩を寄せ合いながら楽しそうに笑い合う人、一人カメラを向ける人。
その誰もが幸せそうに微笑んでいる。
町はすっかりクリスマス一色だ。
彼女は暫くその様子をぼんやりと見つめていた―。
今年の春、彼女は一つ年下の彼と共に通っていた中学を卒業し、スグ近くにある公立高校へ進学した。
彼女がその高校を選んだ理由は、まず制服がおしゃれなブレザーであるし、専願で受ければ絶対に滑らないと云う担任の評価に加え、家からも一駅ほどの距離なので、場所的にも通うには良かった。
それに、先に卒業し、高校へ進学する事を彼は随分と心配していたので、近くなら安心だ、とも付け加わわると、これ以上の条件はなかったが、それでも心配だったのか彼女が卒業してスグに彼は部活を辞めてしまった。
「これまでみたいに一緒に帰ろう」
その日から彼は毎日、彼女の高校まで自転車で乗り付け、後ろに彼女を乗せると今までと同じように二人で下校した。
「部活、せっかく良い感じだったのに、もったいない」
「そんな事ないよ!っていうか、そもそも学校が離れ離れになってるだけで会える時間が短くなるのに、部活なんかやってる場合じゃないよ!それに俺的には俺の彼女だぞ!っていう敵へのアピールでもある!」
いつも真剣で幼い彼が彼女には可愛いらしく、愛おしかった。
「俺も来年になったら絶対、同じ高校に行くから!」
そう言って緩やかな坂道を一生懸命、立ち漕ぎする背中には白いチョークの粉が擦れている。
「黒板か!」
彼女は少し強めに背中を叩くと、粉がふぁっと舞った。
「黒板?」
「背中、チョーク付いてるよ」
「うそ!?」
「うん、学ランが黒いから丁度黒板みたいで、中学生。って感じ」
「まじでー」
ゼイゼイと息を切らせ始めた小さな黒板に彼女は「がんばれ」と指で書きとめた。
―12月18日―
今日は背中にチョークが付いていて、黒板を背負いながら自転車を漕いでるみたいでおかしかった!あの時、私は背中に何て書いたでしょうか?ヒント・来年は去年みたいに同じ学校に通えてたら良いな~です。答えは明日のページで!
彼女は彼と付き合い始めてから日課にしている彼宛てへの日記を書き終えると、残り少なくなってしまったノートを仕舞い、彼にメールを打った。
「お休み!また明日!」
「お休み!また明日も楽しみに勉強頑張る!」
そんなヤル気に満ちたメールから一夜明け、
二人はいつもの様に一緒に下校していたが、どうも彼の元気が無い。
「どうしたの?元気ないじゃん!」
「えっ?そんなこと無いよ!」
彼は笑って見せたが、無理しているのはスグに察しが付いた。
その時、彼女はあえて追及しなかったが、その日の夜のメールはいつもより長めに作った。
「ハロー!今日も送ってくれてありがとね!寒いから無理しないで風引かないように!もし、何かあったらいつでも言ってよ?少なくても先輩なんだから、もしかしたら良いアドバイスができるかもよ☆!ちっちゃな事からおっきな事まで何でもオッケーよ!今日はまだ起きてるから良かったら、電話でもメールでもどうぞ!」
今思えば、スグに返信してくる彼から朝になっても返事が無い事自体、おかしかった。
未送信になっているのではないかと、何度もメールボックスを確認したが、ちゃんと送信済みになっている。
電話を掛けてみても、呼び出し音が鳴っているばかりで応答が無い。
決定的だったのは、放課後に彼が迎えに来なかった事だ。
その日、彼女は彼の家を訪ねたが、誰も居ないようで応答が無い。
仕方が無く、メールを送り、電話を何度か鳴らす他無かった。
ようやく電話が繋がったのが、その日の夜だった。
「もしもし」と電話口に出た声は、聞こえてくるはずの声では無く、ひどく枯れていて只ならぬ雰囲気だ。
サーッと過ぎる不穏な予感に激しく脈打つ胸が苦しく、髪が逆立つ。
受話器からは何かを必死に訴えながら泣き崩れる女性の声が漏れていたが、真っ白になった彼女には何も聞こえなかった。
それから彼が彼女を迎えに来る事はなかった。
詳しい事は何も聞かなかった。
と、いうより聞けなかった。
認められなかった。
―彼はきっと来年の春に私と同じ高校に入学して来るんだ。
だから今は勉強で忙しいに決まってる。
絶対、そうに決まってる。
彼女は二人でいつも帰った道を一人、行ったり来たりと何度も往復した。
メールだって寝る前にはいつもと同じように「お休みなさい、また明日」と送信し続けた。
それから二三日もしない内に終業式を向かえ、学校は冬休みになったが、それでも彼女は夕方になると、いつも待ち合わせた校門に行っては、そこで彼を待っていた。
―明日はクリスマスだよ!たまには自転車に乗らないで、二人で手を繋いでどっか行こうよ!勉強ばっかりじゃ効率悪いし、パーッと二人で遠くに遊びに行こ!
彼女はメールを送ると、暗くなった空を見上げて星の数を数えていた。
「一、二、三・・・」
数えても数えても数え切れない星達は、瞬間瞬間で消えては産まれているようで、そう思うと途端に自分のやっている事がどうしようもなく、虚しく思えて彼女は声を上げて泣いていた。
すると「何やってんの!?一緒に帰ろう!」と声がした。
後ろを振り返ると自転車のハンドルに手をかけた彼が満面の笑みで立っていた。
ハッと目を覚ますと、誰も乗っていなかったはずのバス車内はすべての席が埋まっていて、つり革に摑まっている人も居る。
綺麗なイルミネーションが見えていた窓は密度が濃くなった車内と車外との間に挟まれて、白く曇っていた。
―あいたい―
曇った窓を指でなぞると、その四文字は流れる水滴に消えて、そこからはまた違う景色が覗いていた。
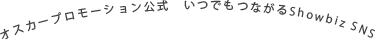

 Login
Login 2 いいね
2 いいね クリップする
クリップする マイアミ―になる
マイアミ―になる









コメント
いいね・コメント投稿・クリップはログインが必要です。
ログインする
不適切なコメントを通報する