小鍋を持った母親の後について玄関を出ると、
「こんばんわー」
程なく開いたドアから顔を出した叔父さんはとても驚いた様子で、
「大丈夫ですか?」
「ぁ、すいません。こんばんわ」
「こちらこそ、夜分にすいません。これ、
「へ?ぇえー!」
ー「その時のことって今でも鮮明なんだよね。
次の日、隣人はピカピカに磨き上げた鍋を返しにやってきた。
高級なカルピスを添えて。
ー「両親は恐縮して、
隣人が添えたものは、明らかに彼女宛てのプレゼントだと思った。
それからは玄関先や近所で姿を見つけると、
それはたった「こんにちわ」と「さようなら」だけだったが、
そんな時は決まって壁をノックする。
コンコン。
コンコンコン。
それは一人さみしく留守番をする彼女にとって暖かい繋がりになっ
ー「それから暫くして、下校途中にばったり叔父さんに会ったの」
いつも一緒に下校する友達とバイバイしてスグの事だった。
「ぉお!こんにちわ」
「あ、こんにちわ」
「今帰り?」
「そぉ」
「じゃあ同じだ。一緒に帰ろう」
叔父さんは抱えていた大きな茶袋に手を突っ込んで、
「これ、良かったらどうぞ」
見ると、
「あ、でも、、、」
「お母さんに叱られる?」
頷く彼女にそれらを持たせると「大丈夫。
「ありがとう」
「どういたしまして」
二人は並んで帰り、ドア前で別れた。
玄関から部屋に戻り、貰ったばかりのお菓子を眺めながら、
共働きの家庭で育った彼女にとって大人は朝から晩まで働いている
おじさんってなにやってるんだろう。
謎めいた優しい叔父さんにどんどん好奇心が刺激される。
今度、一回聞いてみよう。
そう思ったことを忘れぬうちにノートに書き留めた。
その日、帰宅した母親にお菓子の件を話すと、
何と無く予想はしていたが、納得がいかない。
何が悪いのか分から口答えもしないまま、
翌日。
朝早くにゴミ出しに出た母親がドア前で何やらお礼を言っているの
その日も昨日と同じ場所で叔父さんにばったり会い、
ー「もちろん、いけないんだろうな、とはー思った。
それからは毎日、
いつもより早く授業が終わる土曜日でも必ず叔父さんは居る。
そして、必ずお菓子を差し出し、彼女も受け取った。
その事は誰にも黙っていた。
「おじさんっていつも何をしてるの?」
思い出したように彼女は聞いた。
「ん?」
叔父さんは苦く笑いながらそう言っただけで、
聞いてはいけない事をきいてしまった。
どうしよう。
そんな事をおもいながらq、チラリと様子を伺ってみると、
口元は作っていたように思えたが、目がさみしそうで辛い。
見上げてみると、家は目前に迫っていた。
「おじちゃんのお家に遊びたいな」
自分でも何故そんな事を言ったのか、、、、
家の厳しいルールは誰よりも分かっている。
友達と遊ぶ時でさえ事前に申告し、
ー「多分、隣だっていう安心感もあっただろうし、
その日、
~続く~
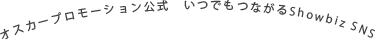

 Login
Login 2 いいね
2 いいね クリップする
クリップする マイアミ―になる
マイアミ―になる









コメント
いいね・コメント投稿・クリップはログインが必要です。
ログインする
不適切なコメントを通報する