ミヒャエル・ゾーヴァの絵を最初にみたのは、多分、絵本でだったと思います。
その柔らかな質感と、画風の鋭さの絶妙なコラボレーションが大好きな作家さんです。
『ミヒャエル・ゾーヴァの世界』(講談社)を読み終えました。
彼の画集であり、たっぷりとしたエッセイも掲載されています。
素敵なアート作品が
ポストカードになっているのは
よくあることですが
ミヒャエル・ゾーヴァの場合は
ポストカードを売ろう!と本人が認識した上でポストカードになっているものが多いんだなということを知りました。
つまり、作家が意図せず、ポストカードにされちゃった、というのではないものが多い、ということです。
一緒に仕事をしていた仲良しのエッターが、ポストカード会社「インコグニート」を立ち上げ、エッターと二人でポストカードを作って売る、ということを始めたと言います。
作品を見ていて思うのは
サイズは非常に重要だということ。
そのサイズで作品を作ったことに、作家の意図とか意思とか、とにかく無視できないものが存在しているのです。
もちろん名画は縮小プリントされても名画として認識できますが、
やはり、作家が作品を作り上げたときの実物大で見ると、違った印象を持つものです。
美術館などで作品を鑑賞した後に、お土産用のポストカードでさっき見たお気に入りの作品が印刷されたカードを買おうと思ったら、うーん違うなあ、と思った経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もちろん、印刷の色や額装がないということの影響もありますが
やはり、ここでもサイズの重要性を改めて意識させられます。
(日本の印刷は素晴らしいので、それでもなるべく実物の色や雰囲気を損なわないように技術が結集されて図録なども作られてはいようなのですが・・・)
ミヒャエル・ゾーヴァの絵には動物がよく登場するのですが
「つまり、人間よりも動物のほうがシリアスになりすぎないですむ。」
と述べられていました。
最初は風景を描いていたゾーヴァですが、
ある時、そこに一匹の動物を描き加えたことからだとか。
「動物を使うようになったきっかけは、風景に付け足しで描いてみたら思いがずドラマがうまれて面白かったからだけれど、絵として、さらにまた別の効果が生まれることに気がついたのだ。」
動物を描き加えたことによって
「なにかおかしなことが絵の中で起きる。」
というゾーヴァ。
見るたびに、違ったドラマを想像させる彼の絵。
それが「なにかおかしなこと」なんです。
それにしても、この本の出版のために日本に来たゾーヴァが知っていた日本語が
「カンパイ」
と
「トリミダシタ」
だけだったというのには笑いました。
構成・翻訳のナスダさんから習ったそうなのですが・・・
日本の旅行中はこの二つの単語の連続だったとか

ま、まあ、ならば教えておいた単語は
合っていたってことかしらね。
大いに実践で活用されたってことで。
ゾーヴァのポストカードをたくさん取り扱っているお店を今年の夏に発見したばかりなので、
改めてそこにもまた行きたくなりました

ゾーヴァの絵でウィルさん似のこが登場する作品とか、あったっけなあ・・・
本日も仲良し。
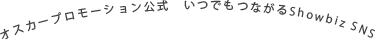

 Login
Login
 9 いいね
9 いいね クリップする
クリップする マイアミ―になる
マイアミ―になる











コメント
いいね・コメント投稿・クリップはログインが必要です。
ログインする
不適切なコメントを通報する