花火大会の当日は夕方から雨が降り出していた。
彼と二人で会う約束をしていた寿美は、彼にキャンセルの連絡をしようかと家の電話の前に座り込み、ずっと考えていた。
窓ガラスを粒になって流れる雨は当分止みそうにもなく、この分でいくと花火大会も中止に違いないが、そんな事はどうでも良かった。
「その時ね、お見合いの話があって」
両親が勝手に決めた縁談だった。
厳格な父親と、教育熱心な母親は一人娘の自分をとても熱心に愛してくれていると思う反面、いつも自分の意見が存在すらしていない事に時々息苦しさと孤独を感じていた。
父親の言う事には決まって「分りました」「ありがとうございます」と言い、母親の言う事には必ず「はい」「そうします」と言った。
学生時代は特に厳しく、部活動も許されなかった。
学校から帰宅すると、家庭教師の先生が、休日には隣町まで父親の運転する車で3つのお稽古事に励み、夜の10時には家中の電気が消えている、といった環境だった。
多感な学生時代にも反抗一つせず、全て両親の言いつけを守ってきた彼女が初めて両親に自分の意見を言ったのは、後にも先にもこの時ただ一回だけだった。
「今、とても大切に思っている男性が居て、私はその人ともっと一緒に居たいです」
父親は烈火の如く激怒し、相手の素性を明かせと喚いた。
夕飯が並べられていたテーブルは目茶目茶にされて、隣では母親が恐怖に固まっている。
「それは言えません」
この時、彼女は彼の身の危険を感じ、とっさにそう答えた。
―パンッ
頭の奥からキーンと耳鳴りが走った。
驚いて見上げた父親は身を震わせて涙を流し、硬く拳を握っている。
「・・・ごめんなさい」
「もう知らん」
父親はそのまま家を飛び出すと、その日は帰ってこなかった。
それから暫く彼女の家は静まり返っていた。
誰も口を開かず、目線すらも合わない。
それは彼女に限定された事ではなく、両親同士も話さなくなっていた。
廊下を歩くときも音を立てぬように抜き足差し足。
時折、母親のすすり泣く声が何処からともなく聞こえてくるようで彼女はどんどん弱っていった。
限界だった。
選択の余地は無い。
それならなるべく早く彼に話をした方が良い、と頭の中では分っていても、あともう一回、最後にもう一回と会っている内に決意が薄れてズルズルと今日になってしまっていた。
どれくらいの時間をそうしていたのか。
膝を抱いたままボーと見つめていた窓から傾いた西日が紅く差し込んでいた。
「今日、ちゃんと言おう」
彼女は自室に戻ると、ドレッサーを開いて髪を結った―。
「こんばんわ」
待ち合わせた時間より早く着いた彼女に彼は優しくそう言った。
「こんばんは・・・早いね」
「うん!今日は話したい事があって、それを考えてたら時間まで待たれへんかった!」
無邪気に笑う彼の顔を彼女は直視できなかった。
「・・・」
「雨、上がって良かった!・・・なぁ?」
と、黙っている彼女の顔を覗き込んだ彼の顔には「何かあったのか?」と書いてあった。
「あんな、」
「ん?」
「・・・あんな・・・」
伝えなければいけないのに、言葉よりも先に涙が零れてしまいそうだった。
「大丈夫か?」
と彼女の手を取ろうとした彼の手を振り払うと、一気に言葉が溢れた。
「私な、お見合いする事にした!だからもう合わない。勝手なことを言って本当にごめんなさい」
泣かないと決めていたのに、彼に下げた頭を上げる事が出来なかった。
「・・うん。・・・そぉなんや」
少しの間、二人はその場に立ち尽くしていた。
すると、静かだった空からまたポツポツと雨が降りだして、あっという間にザーザー降りになった。
「寿美、大丈夫?」
静かに顔を上げてみると、目の前に立っている彼は不器用に笑顔を作って見せていた。
「寿美は優しいからな、」彼は搾り出すように言うと、右手を差し出した。
「寿美の言った事は分かった。送っていくから、帰ろ。今日はきっと花火も上がらんわ」
彼女がその手に触れると、彼は今までには無い位に力強く握った―。
「その彼、事故して未だに帰ってこぉへんねん」
「えっ?」
「その日、そのまま家の近くまで送って貰って別れたんけどな、次の日に彼のお母さんから家に電話があって、バイクで事故して・・・って。でもバイクの免許なんか持ってなかったし、乗ってるところも見たこと無かったから、そんなん信じられへんで、スグに彼の家に行ったら・・・」
彼女の顔を見るなり、彼の母親は声を上げて泣き崩れたという。
「あの子ね、寿美ちゃん乗せて山の上から花火見るんやってゆって、ちょっと前に免許証もらって、喜んで。あの日も天気予報は雨やからバイクは辞めときなさいってゆったのに聞かんと出て行って・・・寿美ちゃんと花火見るんやって嬉しそうにゆってたのに、それも叶わんと・・・可哀想に。」
知らなかった。
彼がそんな事を計画してくれていた事も、彼がその為に教習所に通っていた事も。
「でもあの子、本間に寿美ちゃんと仲良くさせて貰うようになってから母親の私から見ても生き生きしてたし、今年の母の日に初めて手紙くれたんやけど、僕のこと産んでくれてありがとうって・・・本間に親孝行な子やと思ってたとこやったのにこんな・・・」
「警察の人の話しやけど、大分無理な運転したんやろうなって」
美奈子には返す言葉が見つからず、ただ目の前に打ちあがる花火を見つめる他、無かった。
ヒュー・・・・ドーン!
ヒューヒューヒュー・・・ドンドンドン!
「だから、私にもあるよ?」
「・・・え?」
「この気持ちは誰にも分からんって思う事」
叔母さんは真っ直ぐに美奈子を見て静かにそういった。
「来年は素敵な彼でも連れておいで」
叔母さんは温くなったビールを一気に飲み干すと、美奈子の背中を思いきり叩いた。
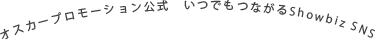

 Login
Login 2 いいね
2 いいね クリップする
クリップする マイアミ―になる
マイアミ―になる









コメント
いいね・コメント投稿・クリップはログインが必要です。
ログインする
不適切なコメントを通報する