「こんにちは!」
下校途中、さゆは誰かれ構わずに挨拶しまくっていた。
「さゆちゃんは偉いね~」と大人に褒められるのはとっても気
分が良い。
少し前までは親が迎えに来てくれるのを待っていなければなら
ない保育園生だったが、春に晴れて小学生になり、今ではこう
して一人で学校と家を行き来しているのだと思うと、まだ馴染
まないピカピカのランドセルが誇らしい。
彼女にとってランドセルは大人の証明のようで、とにかく自分
が背負っている姿を見て貰いたくて仕方が無かった。
その日、彼女は我が家があるマンションの前まで帰ってきた
が、ふと思い立った様に踵を返した。
通っていた保育園の先生たちに自分がおねいさんになった姿を
見てもらおうと思いついたのだ。
家から保育園までは家の前の大きな道路を道なりに真っ直ぐ歩
いて15分程度の距離なので、誰にでも簡単だった。
―ひとりで、ランドセルをせおって私が来たらきっとせんせい、
びっくりするなー!
そんな事を思いながら、彼女は脇を走る車を横目にまっすぐ進
んだ。
―あれ?
丁度、半分ほど来たところで空を見上げてみると、パラパラと
感じた雨が、あっという間にザーっと降り始め、驚いた彼女は
目に付いたバス停の屋根に飛び込んだ。
―うわっ!
遠くの空がピカリと光り、鳴り響く大きな雷の音に肩が竦む。
ムッと湿気た空気に湿った髪が頬に張り付いた。
困ったように頬を掻きながら、仕方が無いので誰も居ないベン
チに腰掛けると、再び空が蒼白く光り、雨音もソレと競う様
だ。
足をブラブラ、ふんっ、と大きく息をはいてみると、被ってい
た帽子のツバから水滴がポツ、ポツ、と丈の短いズボンから覗
いた膝に続いて落ちた。
それを人差し指で撫でて線にしながら雨が止むのを待っていた
が、一向にその気配は無い。
―せんせいに見せるのは今度でいっか!
彼女が折れそうになっている自分を励ますように立ち上がる
と、同じように雨が止んだ。
この機を逃さぬように来た道を急いで帰ろうと、彼女は駆け
た。
背後では音も無く濃霧が彼女に迫っている。
気が付けば、彼女は泣き出していた。
真っ白で何も見えない。
うっすらと見えている景色に見覚えも無く、自分が何処に居る
のか全く分からない。
帰ろうにも何処に向いて進めばいいのか分からなくなってい
た。
蹲り、ひたすらに母の名を呼んでみても、何も起こらなけれ
ば、誰も来てはくれなかった。
仕方が無く立ち上がり、注意深く周りを見渡してみても見たこ
とがない石垣や大きな木が生い茂っているだけで、自分家のマ
ンションや、さっきまであったバス停も見当たらない。
ふと足元を見てみると、いつの間にか砂利道の上に居る。
どこかを曲がったわけでも、入り組んだ路地を来たわけでもな
い。
家の前の道を真っ直ぐに来ただけなので、真っ直ぐに引き返せ
ば戻れるはずなのだが、今の彼女にはどの方向がまっすぐなの
かも分からない。
自慢のランドセルも今となっては、後ろ髪を引く錘でしかな
く、耐え難いほどに重く感じられる。
湿った洋服や、靴がむず痒く彼女がまた大きな声で泣き出した
時だった。
♪~あ~おいぃ~そぉ~らぁ~あにぃ~♪
それは音楽の時間に習っている校歌だった。
振り返ると、自分と同じくらいの女の子が歌っている。
「こんにちわ!」
さゆがそう言いながら駆け寄ると、彼女はニッコリと微笑ん
だ。
「こんにちは」
長いおさげが特徴的な彼女は淡いピンクのアジサイを手にして
いた。
「ここってどこですか?」
再びニッコリと微笑んだ彼女は、さゆの後ろを指差した。
「え?」
さゆが指の先に目をやると、すぐ傍に自分家のマンションが見
えた。
「あっ!ありがとう!」
「いいの、」
「じゃあね!」
「コレ、」
彼女は肩から掛けていた鞄から真っ赤な鈴を取り出すと、さゆ
に差し出した。
「なに?」
「あげる、もってて」
「いいよ!ひとからなにかもらったらママにおこられるから、
ごめんね」
「じゃあ、」
と彼女はさゆに手を翳し、それからゆっくりと手を振った。
「ばいばい!」
さゆは全速力で家の前まで駆けた。
その日からだった。
さゆの体から鈴の音が聞こえるようになったのは―。
まるで身に着けているようにさゆが身動きすると、リンリンと
鈴が鳴る。
更にそれは、本人だけでなく、さゆの母も父も皆が耳に出来る
ほど鮮明で、授業中には極力動かないようにしていなければ、
鈴探しが始まった。
何故、こうなったのか分らないまま時は流れた。
「じゃあ、ママは今でも鈴の音が聞こえるの?」
「うんん、随分前に聞こえなくなっちゃったの」
「どうして?」
さゆは5年生になっていた。
「この辺りは昔、アジサイ山と呼ばれていたほど、梅雨の時期
には美しいアジサイが一面に咲いていたと云われていますが、
今ではこの様に開発が進み―」
社会の先生が言うには、さゆが通う校舎は昔そのアジサイ山の
中腹に立っていて、その頃の生徒達は随分と苦労して通学して
いたらしいが、開発が進み、山の木は倒され、美しく咲いてい
たアジサイも駅前の植え込みに少し残るのみとなったらしい。
その日の放課後―。
さゆは教室の窓から校庭をぼんやり眺めていた。
今年の春、母が通った小学校に入学した娘のあさひは校庭の隅
に植えられた無数のアジサイに水をやっていた。
「いっぱいお水のんで、きれいなお花さいてね!」
そうやって、あさひは来る日も来る日も水をやっている。
「あ!またあした!」
チャイムを聞き、校舎へと戻っていくその姿を見守るようにリ
ンと小さく鈴の音が零れているのを彼女は知らない。
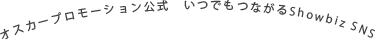

 Login
Login 2 いいね
2 いいね クリップする
クリップする マイアミ―になる
マイアミ―になる









コメント
いいね・コメント投稿・クリップはログインが必要です。
ログインする
不適切なコメントを通報する