「それね、隣に住んでた叔父さんがくれたやつなんだ」
彼女は部屋の片隅にあるラジカセを指差した。
下には毛足の長いタオル地のマットが敷いてあって、ボディーにも綺麗なタオルが掛けられているので、大切にしているのだというのが伝わってくる。
「へぇ~そうなん?」
「うん」
「まだ使えるの?」
「うんん、とっくに壊れちゃったんだけどね~」
彼女とは会ったり、会わなかったり、だが、なんだかんだでもう8年くらいになる。
会わない時は1年くらい全く連絡もしないが、会う時は週2ペースといった感じだ。
年齢も身長も同じなので、似てない双子だと私は勝手に思っている。
何より私がそう思うのは、一緒に居ると考えている事が分るというのか、自然に伝わってくるので彼女には変な気を使わなくて済むからだ。
それはなんとなく、あ、機嫌が悪いなといった時もあれば、具体的に彼女は今喉が渇いているけど、飲みたいのはお水ではないんだろうなといった時もあって、二人で出かけていても「次、どうする?どうする?」みたいな小会議は起きない。
そんな事を他愛もない話をしている時に話すと、彼女は「同じだ」と言った。
彼女にも私の事が手に取るように分るらしい。
つい先日は開口一番「つい最近、良い事あったでしょう?」と言われてドキッとした。
「なんで?」
と聞いてみると、「いつもと顔が違う」と言うので、「化粧してるからじゃないの?」と返すと彼女はニヤリと笑った。
私自身が分りやすい人間だという事を差し引いても、彼女はよく私の事を言い当てる。
新しく出来たお店にご飯を食べに行くと、メニューを見れば私の食べたい物が分るらしい。
実際にそれは当たっているし、驚いたのは去年の夏。
何気なく点けていたテレビでハワイの特集を見ていると、その番組ではローカルのキルティングショップが紹介されていた。
そこの店員さんは全ての商品が手作りで同じデザインは二つと無いのがこの店の特徴ですと言っていて、画面には可愛い小物入れが幾つかとショップの住所などが映っていた。
「へぇ~可愛い~」と思っていたら、まさにそのショップのその小物入れを彼女がお土産に買って来てくれたのだ。
そぅいえば、ハワイに遊びに行くというのは聞いていたが・・・といった事が細々と多々ある。
そんな彼女が最近になって少し広い部屋に引っ越したので、一緒に夕飯を食べようと誘ってくれた時にさっきのラジカセの話になった。
「子供の頃、超貧乏でさ~テレビも無かったの。で、当時両親とアパートに住んでたんだけど、隣におじさんが一人、引っ越してきたのね」
学校から帰って自由帳を開いていると誰かが薄いドアをノックした。
当時、小学1年生だった彼女は共働きの両親から「知らない人と話してはいけない」と強く言いつけられていたので、ハッとした。
ドアの外からは「こんにちはー」という声がする。
抜き足差し足で玄関まで行き、ドアにそっと耳を当ててみると「居ないかな~」という声が小さく聞こえた。
暫くそうしていると、去っていく短い足音の後に隣のドアが閉まるのが分かった。
夜。
両親が帰宅すると、見知らぬ男の人が尋ねてきた。
名前を加藤と言った。
「隣に引っ越してきました、加藤です。よろしくお願いします」
男の人は丁寧に頭を下げると、洗濯用洗剤を母親に手渡した。
「あぁ、ご丁寧にありがとうございます。お一人ですか?」
「はい、単身頑張っております」と加藤は笑った。
「でね、次の日に学校から帰ってきたら加藤のおじちゃんが玄関から出てきたところだったの」
小さな背中に大きなランドセルを背負った彼女を見るなり、加藤は「こんにちは」と言った。
瞬間、両親の言葉が過ぎったので、軽く頭を下げると、急いで玄関のドアを開いた。
振り返り様に、閉まりかけたドアの隙間から寂しそうな加藤の顔が見えたという。
「なんか、罪悪感じゃないけど、悪い事したなって子供心に思った」
その次の日。
玄関の前に加藤は居なかったが、いつものように自由帳を開いていると、壁の向こうから話し声が聞こえてきた。
テレビの様だった。
何を言っているのかまでは分からなかったが、彼女は例のごとく耳を当て、様子を伺っていた。
時折、「ふ」と笑う加藤の声が混ざった。
「あ、笑った」
そんな事を思いながら隣の音を盗み聞くのが楽しくなった彼女は、学校から帰ると決まってそうするのが日課になっていた。
ある時、いつもの様に隣の壁に耳を当ててみると、何も聞こえない。
こんな事は初めてだった。
もしかしたら居ないのかも知れないと思い、なんとなくの好奇心から壁をコンコンとノックしてみた。
すると、ノックが返ってきたので、ビックリした。
「どうしよう」
と思いつつも、もう一度、壁に耳を当ててみると、ゴホゴホと咳き込んでいるのが聞こえた。
「あ、風邪、ひいてる」
そう思うと少しだけ親近感が湧いた。
その日の夜。
「これ、もう明日までもたないと思うから全部食べてしまってね」
二日目に突入したおでん鍋をつつきながら母親が言った。
一足早く夕飯を終えた父親は早々と銭湯に出かけて行ったので、部屋には二人きりだ。
「となりのおじちゃんに持っていったら?」
そう言うと母親は流しの下から小鍋を取り出し、煮崩れていないものからそこへ移し始めてので、彼女は少しワクワクした。
「私も行くー」
彼女は母親のズボンの裾を掴むと、そのまま付いて出て、昼間と同じように隣のドアをノックした。
~続く~
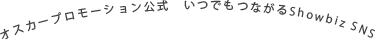

 Login
Login 2 いいね
2 いいね クリップする
クリップする マイアミ―になる
マイアミ―になる









コメント
いいね・コメント投稿・クリップはログインが必要です。
ログインする
不適切なコメントを通報する