やばいな、と思った頃にはもう遅かった。
さっきまではかろうじて見えていた風景も、既に墨をかぶった様に真っ黒で、ひたすらに真っ直ぐに進んでいればいつか道に出られるはずだと、自分を奮い立たせていたが、こうなってしまってはその真っ直ぐすらも分らない。
やけくそになってしまいたい気を抑え、初めて歩みを止めてみると、毛穴からダラリと汗が湧いた。
Tシャツの裾でそれを拭いながら、改めて辺りを見回してみたが、本当に何も、何一つも見えない―。
ドッと疲労が肩に乗ると、気も萎え、ため息も続いて出た。
こんな時に人は空を見上げるのだと、見上げた空には星たちが美しく輝いている。
それは余りにも美しく、気が付けばその場に腰を下ろしていた。
その日の朝。
仕事仲間三人と英里子は登山に出かけた。
そもそも彼女は登山に微塵の興味もないし、休日は、、、というより時間さえあればクタクタの布団の上に居たい方なので、乗り気ではなかったが、毎日ランチを共にしている手前、断りきれなかった。
山に入ったのは午前8時頃だ。
それほど標高が高いわけではないその山の頂上で弁当を食べ、日が沈む午後5時頃には戻っている予定だった。
予備知識の無い初めての登山とあって、あれやこれやとリュックに詰めて来ていた英里子を他の三人は笑った。
「あんた、山脈でも越えるつもり?」
結局、ペットボトルと弁当以外は車の中に残し、彼女は出発した。
「待ってー!」
英里子を置いて、三人はすいすいと登って行く。
不慣れな山道に、運動不足が祟り、山に入って15分もしない内に帰りたかった。
彼女の足首もパキパキと同感のようだ。
「早く、早くぅー」と言う三人の背中を見ながらも何とか山頂に辿り着いた。
確かに、そこからの景色は素晴らしいし、何の味気も無いいつもの手作り自前弁当も恐ろしく美味しい。
がしかし、そんな感動も束の間。
これから来た道を戻るのかと思うと、此処に留まるのもありなのではないかと疑えてならない。
「あほか!」とまた三人が笑う。
「じゃあ、私が少し早めに出発するから皆は10分後位に出てよ!一人だけ最後ってやだからさぁ」
英里子の運命が狂ったのは自分のこの一言からだが、特別に何かズルをしようとした訳でもなく、ただ来た道を戻っただけだったので、何故自分が今、迷子になっているのかが分らない。
それに登山途中には沢山の人ともすれ違っていたので、誰かしら目に付いても良さそうなのだが、人っ子一人居ないのも腑に落ちなかった。
選択肢は無い。
英里子はひたすら真っ直ぐに進もうと決めた。
此処に腰を下ろしてどれくらいの時間が経っただろうか。
極度の疲労からくる眠気に、未だかつて無い程の睡眠欲を掻き立てられた。
いっその事、この場に寝転んでしまいたいが、理性がそうはするなと云う。
その戦いの中でうつらうつらしていると背中に程よい樹をみつけたので、そっともたれかかってみると、遂に落ちてしまった。
「樹って、温かい」
薄れ行く意識の中で英里子はそう思った。
「英里子さーん!英里子さーん!」
何となくそう呼ばれた気がして目を覚ますと、遠くに明かりが揺れているのが見えた。
「あ」
自分を探しに来てくれたんだと、彼女は「おーい!」と叫んでみたが、届いていない様子で、明かりはどんどん小さくなっていく。
「待って!」
彼女は立ち上がると、両手をブンブン振りながら障害物にぶつからない様、注意し明かりを追った。
「此処です!此処にいまーす!」
尚も届かないのか、明かりは遠ざかっていく。
その内に爪の先ほど見えていた明かりも無くなり、また真っ黒いだけの空間になった。
「おーい!!誰かー!」
しばらくの間、彼女は叫んでいたが、それも闇に飲み込まれ、何も返ってこない。
仕方が無く、彼女はまたおずおずとその場に腰を下ろし、膝を抱いた。
「でも、誰かが探してくれているって事だよね?」
そう自分に言い聞かせ、再び空を見上げながら気長に待つことにした。
手探りでもたれられそうな樹を探す。
すると、すぐ傍にまた大きな樹を見つけ、そっと寄りかかった。
―やはり樹は温かい。
「樹も本当に生きているんだ」
彼女はこの時、命に触れた気がした。
それから程なくして、彼女はまたあの光を見つけた。
今度は上手くいったようで、こちらに駆けてくるのが分かる。
「助かった」
無数の懐中電灯の光が彼女を照らし出したので、何も見えなかった視界が一気に開けた。
思わず駆けだした彼女は無事に保護され、その時に初めて涙が出た。
「本当にありがとうございます」
彼女は消防団員の一人に抱きつきながら、ワンワン泣いた。
「歩けますか?」
「はい」
彼女は救助に来てくれた数人の男性とゆっくりと下山を始めた。
「寒かったでしょう?」
そう言って一人が斜めに掛けていた水筒のコップを差し出した。
注がれた茶から白い湯気が上がる。
「はい、でも樹が温かいのには驚きました。やっぱり生き物は温かいんですね」
「へー、それは初めて聞いたですね~」
「本当ですか?背中が凄く温かくて眠ってしまったくらいです」
「ふぅん」
その人は驚いているようだった。
「こんなに細い木々でも温度はあるんですね」
と懐中電灯を当てた林の木々はどれも細く、ひょろ長かった。
その時に初めて英里子は少しの違和感を覚えた。
背中全体を包み込めるほどの大木が見当たらないのだ。
「まぁ、暗いから見えないのかな」
後日、同じメンバーで再チャレンジした登山では、痴漢注意の看板は見つかったが、英里子の背中を包み込める程の立派な樹は一本も見つからなかった。
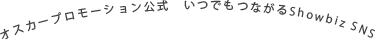

 Login
Login 2 いいね
2 いいね クリップする
クリップする マイアミ―になる
マイアミ―になる









れおんさんの短編には、人が独りになったり、道に迷ったりしていても、得体の知れない自然のちからというか、神秘的ななにかがあって、それが人をほっとかないはずだという、世界観が見られますね。
僕は田舎に住んでいるので、つねに虫の声や、地平線に囲まれながら生きています。
頭の中が行き詰まったとき、夜にふと外を見てみれば、綺麗な星空や、その虫の声やら、カエルの声やら、生命が合唱して、世界は本来なら美しいものだ、人間はそれにさえ気づけば、不幸になんてなりようがない、ということを教えてくれます。
それは懐かしい感覚です。もう子供のときに忘れてしまって、今は思い出すのも難しい感覚なんですね。
だから、都会では、道に迷ったり、暗闇に立たされたとき、人間はどうするのだろうか、と思うと、少し怖くなる気がしますね。
そういうのも、良かったら一度書いてみて欲しいです。